5月13日の10時半から、京都東山の「得浄明院」での「式包丁」の奉納が始まりました。

式包丁というのは、平安時代から伝わる宮中の儀式のひとつ。包丁と箸で、一切手を触れることなく、食材を切り分け、吉祥を表す景色を奉納します。
「また、ギリギリになっちゃった~」とミモロは、急いで「得浄明院」に

明治27年に信州善光寺の京都別院として建立された浄土宗の尼門跡寺院。皇室の御血筋である伏見宮家の方が、ご住職をお務めになっています。
4月下旬から見ごろを迎える「イチハツ」の花でも有名な寺院ですが、すでに「もうお花残ってない…」とミモロ。

庭にいたミモロを見つけてくださったのは、この式包丁を奉納する「庖勝一條流」三代目お家元の、富田さん。

「ミモロちゃん、こっち~」と、すでに参拝者で満席の本堂に別のルートで導いてくださいました。
「わ~すごいいっぱい~」本堂には、この儀式を見にいらした観光客やお寺の信徒さんなどでいっぱいです。

無事に本堂に入れたミモロ。お寺の方の計らいで、なんと内陣から拝見することに…。
10時半過ぎから始まった式包丁。まずは、豆腐を切り分けて、吉祥の文字を作ります。

柔らかい豆腐を、庖丁と金属の箸で切り分け、挟み、盆に持ってゆきます。
「わ~すごいね~」と、冷ややっこも箸で口元に運ぶのは、大変なミモロ。「スプーンじゃないと食べられない…」と。
指先の微妙な感触を調整して、豆腐を傷つけないように運ぶのは、技術が必要。
そして、次は、お家元が、熟練した技を披露。

式包丁は、儀式なので、始まりから終わりまで、流れるような動きで、まるで舞うような雅な動作が続きます。
「長い金属のお箸の扱いが見事だね~」と。ただただ見惚れるミモロです。
お家元が奉納する食材は、筍です。

生の筍の皮を剥き、切り分けます。「ミモロの家の庖丁だと、筍切るのすごく大変…」と、あの~ね~比べる基準が低すぎます。
スパっとというより、滑るように、硬い筍とは思えない切り具合です。

「カッコいい~」と、内陣から拝見するミモロ。

美しい所作が、参拝者を魅了してゆきます。

今回、境内にある芸事の神様「白天龍王」に奉納した2点の作品。
豆腐の「癒し」は、「う~画数が多くて計算するの大変そう…」とミモロ。

式包丁で切る食材は、全部使われ、余るということはありません。つまり、豆腐全体から、どれくらいの大きさで切り分けていくか、緻密な計画が必要なのです。
そしてお家元の筍は、「葵祭」の御所車で、そこに白龍が乗っています。

筍の輪切りの車輪に乗った御所車。菖蒲の花も添えらえて、美しい景色を作っています。
「白天龍王」の社に奉納。

無事に儀式が納められました。
参拝者に囲まれたみなさん。

「ミモロちゃん、よく見れましたか?」とお家元。

「はい、おかげさまで…」とお礼をいうミモロ。
「今年も、しっかり見学なさってましたね~」と、小笹さん。

お家元も、小笹さんも、有名料理屋さんの料理長なのです。
「あの~ご住職は、今日はお姿見えなくて…」と、いつもミモロを可愛がって下さるご住職に会えなかったことが寂しいミモロ。
「はい、御元気ですよ~でも、今日は、ちょっと奥にいらっしゃるんです」とお寺の方。

ミャクミャクの姿をご住職にも見て頂きたかったミモロでした。
でも、ミモロのミャクミャクは、すでに顔なじみの方々に「すごい!ミモロちゃん、可愛い!」と笑いを誘うことに…。
みんなの笑顔に包まれて、本当に幸せなミモロです。
式包丁が奉納された社…神様もお喜びのことでしょう。

「またね~ご住職によろしくお伝えください~」と手を振ってお寺をあとに…

近くの白川には、青々と柳が茂り、五月の爽やかな風が枝を揺らしていました。

5月15日は、「葵祭」。京都の夏の始まりです。
<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより
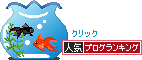 人気ブログランキング
人気ブログランキング
ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、[email protected]まで

式包丁というのは、平安時代から伝わる宮中の儀式のひとつ。包丁と箸で、一切手を触れることなく、食材を切り分け、吉祥を表す景色を奉納します。
「また、ギリギリになっちゃった~」とミモロは、急いで「得浄明院」に

明治27年に信州善光寺の京都別院として建立された浄土宗の尼門跡寺院。皇室の御血筋である伏見宮家の方が、ご住職をお務めになっています。
4月下旬から見ごろを迎える「イチハツ」の花でも有名な寺院ですが、すでに「もうお花残ってない…」とミモロ。

庭にいたミモロを見つけてくださったのは、この式包丁を奉納する「庖勝一條流」三代目お家元の、富田さん。

「ミモロちゃん、こっち~」と、すでに参拝者で満席の本堂に別のルートで導いてくださいました。
「わ~すごいいっぱい~」本堂には、この儀式を見にいらした観光客やお寺の信徒さんなどでいっぱいです。

無事に本堂に入れたミモロ。お寺の方の計らいで、なんと内陣から拝見することに…。
10時半過ぎから始まった式包丁。まずは、豆腐を切り分けて、吉祥の文字を作ります。

柔らかい豆腐を、庖丁と金属の箸で切り分け、挟み、盆に持ってゆきます。
「わ~すごいね~」と、冷ややっこも箸で口元に運ぶのは、大変なミモロ。「スプーンじゃないと食べられない…」と。
指先の微妙な感触を調整して、豆腐を傷つけないように運ぶのは、技術が必要。
そして、次は、お家元が、熟練した技を披露。

式包丁は、儀式なので、始まりから終わりまで、流れるような動きで、まるで舞うような雅な動作が続きます。
「長い金属のお箸の扱いが見事だね~」と。ただただ見惚れるミモロです。
お家元が奉納する食材は、筍です。

生の筍の皮を剥き、切り分けます。「ミモロの家の庖丁だと、筍切るのすごく大変…」と、あの~ね~比べる基準が低すぎます。
スパっとというより、滑るように、硬い筍とは思えない切り具合です。

「カッコいい~」と、内陣から拝見するミモロ。

美しい所作が、参拝者を魅了してゆきます。

今回、境内にある芸事の神様「白天龍王」に奉納した2点の作品。
豆腐の「癒し」は、「う~画数が多くて計算するの大変そう…」とミモロ。

式包丁で切る食材は、全部使われ、余るということはありません。つまり、豆腐全体から、どれくらいの大きさで切り分けていくか、緻密な計画が必要なのです。
そしてお家元の筍は、「葵祭」の御所車で、そこに白龍が乗っています。

筍の輪切りの車輪に乗った御所車。菖蒲の花も添えらえて、美しい景色を作っています。
「白天龍王」の社に奉納。

無事に儀式が納められました。
参拝者に囲まれたみなさん。

「ミモロちゃん、よく見れましたか?」とお家元。

「はい、おかげさまで…」とお礼をいうミモロ。
「今年も、しっかり見学なさってましたね~」と、小笹さん。

お家元も、小笹さんも、有名料理屋さんの料理長なのです。
「あの~ご住職は、今日はお姿見えなくて…」と、いつもミモロを可愛がって下さるご住職に会えなかったことが寂しいミモロ。
「はい、御元気ですよ~でも、今日は、ちょっと奥にいらっしゃるんです」とお寺の方。

ミャクミャクの姿をご住職にも見て頂きたかったミモロでした。
でも、ミモロのミャクミャクは、すでに顔なじみの方々に「すごい!ミモロちゃん、可愛い!」と笑いを誘うことに…。
みんなの笑顔に包まれて、本当に幸せなミモロです。
式包丁が奉納された社…神様もお喜びのことでしょう。

「またね~ご住職によろしくお伝えください~」と手を振ってお寺をあとに…

近くの白川には、青々と柳が茂り、五月の爽やかな風が枝を揺らしていました。

5月15日は、「葵祭」。京都の夏の始まりです。
<ブログを見たら 金魚鉢をクリックしてね 応援よろしく!ミモロより
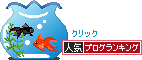 人気ブログランキング
人気ブログランキングミモロへのお問い合わせ・ご要望は、[email protected]まで





























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます