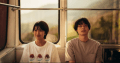早川千絵監督の『ルノワール』が公開された。早川監督は長編映画デビュー作『PLAN75』がカンヌ映画祭「ある視点」部門新人監督賞特別表彰を受けて注目された。そして第2作の『ルノワール』は早くもカンヌ映画祭コンペティションに選ばれた。無冠に終わったが、今年の注目作に間違いない。地方都市(クレジットで岐阜で撮影されたと判る)に住む沖田フキ(鈴木唯)は母親(石田ひかり)と父親(リリー・フランキー)と暮らすが、父親はいま入院中である。感受性豊かなフキはこの父の入院を通して、「大人の世界」に足を踏み入れていく。映画はその様子を1987年の「ある少女のひと夏」として提示する。
冒頭がよく理解出来ないと思うと、それは夢だった。続いて学校で作文を朗読しているが、それは「みなしごになってみたい」という作文で、母親が学校に呼ばれてしまう。母は「勝手に親を殺すな」と叱るけど、フキにはほとんどこたえない。このフキを演じる鈴木唯(2013~)が実に見事で、驚くべき存在感で思春期の入口に佇む不安感を見せている。監督は影響を受けた映画として『ミツバチのささやき』『お引越し』『ヤンヤン夏の想い出』を挙げているが、特に相米慎二監督『お引越し』を思い出す作品。
父が入院中だが、母は管理職になって多忙。父親はガンなので、特効薬を求めて怪しい療法に手を出したり、いろいろと大変だ。一人でいることが多いフキは、子どもの目で大人世界を探っている。マンションにいる女性(河合優実)と知り合うと、彼女の大変な話を聞く。英会話教室に通っていて、そこで知り合った友だちの家に行くと自分の家と全く違うのに驚くが、彼女も引っ越していく。そんな時に「伝言ダイアル」の存在を知り、つい電話してしまったりする。ちなみに「伝言ダイアル」は1986年から2016年までNTTが提供していたサービスで、固定電話からしか利用出来ない。「出会い系サイト」的に使われたケースも多かった。
母もいろいろあることを娘は感じ取るが、忙しい母親とはなかなか話す時間もない。夏休みにキャンプファイアに行くとやはり楽しいけれど、家に帰るとふっと電話してつながった相手に会いに行ってしまったり。まさに揺れる少女の心をエピソードのつながりで、点描していく。題名はフランス印象派の画家ピエール=オーギュスト・ルノワールのことで、作中で主人公の少女フキが「イレーヌ・カーン・ダンヴェール嬢」を買って貰うエピソードがある。そこからこの映画も「印象派」的な作品とする論評もある。
先に挙げた『お引越し』は、両親が離婚する家庭を娘の視点で描いた。一方『ルノワール』は「父の不在」を娘だけでなく周囲にも視野を広げて見つめる。ただ原作のある『お引越し』の方が物語的にはまとまっていて、『ルノワール』はエピソード羅列的になっている。どっちが上とは決められないが、僕はフキが揺れながらも、どう変貌していったか、もう少し知りたいと思った。映画は詩的な映像を提示して観客に想像して貰う作り方。『国宝』『フロントライン』の重量級の圧倒的な物語を見てしまうと、幾分淡彩に見えるのは否定できない。そこが観客動員にも影響しているかもしれない。(あまりヒットしてない感じ。)
前作『PLAN75』は興味深い映画だったが、ここでは紹介しなかった。高齢者の描き方に納得出来なかったのである。製作当時80歳を越えている倍賞千恵子を75歳役に起用していたが、まだまだ元気そうで設定に納得出来なかった。今回の『ルノワール』は洗練の度合いが上がって違和感なく見られるが、鈴木唯の存在感をどう生かすかという観点では、『お引越し』の田畑智子の方が印象に強い。才能ある監督であることは間違いないので、今度は原作ものか自作じゃない脚本で撮ってみて欲しい気がする。